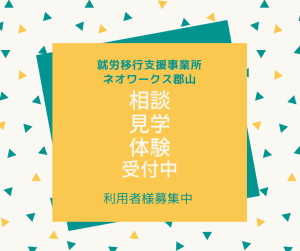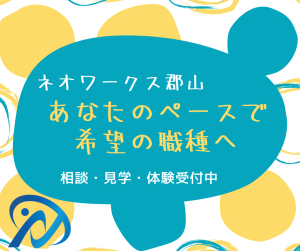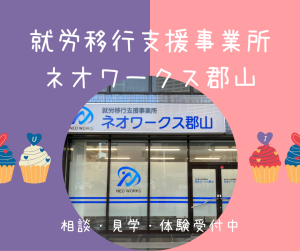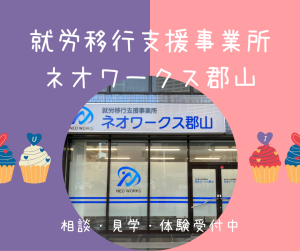
みなさんこんにちは☺
生活支援員 國分です🌟
みなさんいかがお過ごしでしょうか。暑いのが大の苦手な私はもうすでに瀕死状態です…。
さて今回は障害者雇用についてみなさんと考えていきたいと思います‼
障害者雇用枠ってなに?障害者雇用枠で就職したいけど自分は対象かな…企業で障害者雇用について考えている、などお悩みな方の参考になりましたら幸いです💕
障害者雇用とは…
障害者雇用とは、国が定める〖障害者雇用促進法〗に基づき行われる雇用のことになります。障害のある方の場合、障害のない方と同じように就職活動をしたとしても、うまくいかなかったり、就職後に症状や特性による困難を感じることがあります。もちろん全員ではありませんが、状況に悩む方も少なくはありません。
そういった悩みを解消するため、国では障害のある方の就職における選択肢のひとつとして、企業による障害者雇用の制度を整えています。
具体的には、事業主へ〖障害のある方を一定以上の比率で雇用すること〗〖合理的配慮を提供する〗などを義務付けています。
障害者雇用促進法とは…
障害者雇用促進法の正式な名称は【障害者の雇用の促進等に関する法律】です。
障害者雇用促進法の目的は、障害のある方が安定的な職業に就けるようにすることです。この目的を実現するために障害者雇用促進法ではさまざまな内容を定めています。
障害者雇用と一般雇用との違い
・募集時から障害のあることを開示して就職
・募集時は障害のあることは非開示だったが入社してから開示した
・就職後に障害のあることが分かり障害者手帳を取得した
これらはいずれも【障害者雇用】となります。
障害者雇用と一般雇用の違いで分かりやすい例は「採用をするときに就職希望者から障害があることを申告されているか、いないか」になります。
そもそも日本では「就職するときに障害があることを企業へ必ず知らせなくてはいけない」という決まりはありません。
障害をお持ちでも一般雇用での就職は可能です。しかしその場合は、障害の特性によっては、勤務時間(残業が多い)や職場の環境、業務内容などがつらくかんじてしまっても対処をお願いすることが難しくなってしまう場合もあります。
その点、障害者雇用では、雇用主と被雇用者で話し合い、合理的配慮の得やすい環境を整えやすいという特徴があります。
障害者雇用の対象となる方
障害者雇用の基となる、障害者雇用促進法の対象となる方を見ていきましょう。
・身体障害者(身体障害者手帳を持っている)
・重度身体障害者(身体障害者手帳の1級・2級を持っている)
・知的障害者(療育手帳もしくは知的障害者判定機関の判定書を持っている)
・重度知的障害者(療育手帳もしくは知的障害者判定機関の判定書を持っている)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を持ち就労が可能な状態にある)
・その他(心身に上記の機能障害があるが障害者手帳を持っていない)
※知的障害者判定機関は自治体によって異なりますが「心身障害者福祉センター」や「障害者職業センター」「児童相談所」などが挙げられます。
また【その他】の項目には、精神疾患や高次脳機能障害などがあるものの、障害者手帳を持っていない方などが当てはまります(医師の診断書や意見書により判断されることが多い)
障害者雇用率制度の対象者
障害者雇用促進法では、対象事業主へ雇用している人のうち一定の割合以上が障害のある方となるように義務付けされています。(法定雇用率)
このとき雇用義務の対象となる方を〖対象障害者〗と呼びます。
そして対象障害者に当てはまるのは以下の方になります。
・身体障害者・重度身体障害者(身体障害者手帳所持)
・知的障害者(療育手帳もしくは知的障害者判定機関の判定書を所持)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を所持し、就労が可能な状態にある)
注意点として、障害があったとしても障害者手帳を所持していない場合は対象とならないということです。
障害者雇用率制度とは
障害者雇用率制度とは、事業主(国・地方公共団体・民間企業など)は障害のある方を法定雇用率の相当する人数以上雇用しなければならないと定められている制度です。法定雇用率とは、法律上満たすべき労働者全体に対する障害のある方の割合を表したものです。
現在の法定雇用率
2024年7月現在の法定雇用率は下記の通りになります↓
・民間企業…2.5%
・国、地方公共団体…2.8%
・都道府県等の教育委員会…2.7%
つまり民間企業を例に挙げると、100人の労働者がいる場合、そのうち2.5人(2.5%)は障害のある方を雇用する義務がある、ということになります。
このことから、民間企業の場合〖常時雇用する労働者が40人以上〗の事業主は、障害のある方を1人以上雇用しなければなりません。ただし、人数の計算方法は障害の種類や程度によっても異なります。
障害の種類や程度によって計算方法が変わる
基本的には、1人を〖1〗として計算しますが、場合によっては1人を〖2〗や〖0.5〗〖0〗で計算することもあります。
具体的な例は以下の通りになります。
・重度の身体障害がある方(障害者手帳1級.2級):2
・重度の知的障害がある方(障害者手帳A区分等):2
・短時間労働者(1週間あたり所定労働時間20時間以上30時間未満):0.5
・超短時間労働者(1週間あたり所定労働時間20時間):0
条件が2つ当てはまる場合は数字をかけて計算します。
例えば、重度の身体障害のある方が短時間労働者である場合〖2×0.5=1〗となるので〖1〗で計算されます。
ただし、精神障害者の場合、短時間労働の場合であっても下記2つの条件を満たす場合は〖0.5〗ではなく特例措置として〖1〗として計算されます。
・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内
・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
法定雇用率は変動する
法定雇用率は、日本で働いている労働者の数や失業者数、対象障害者の人数をもとに基準値が決まっています。
具体的には下記の計算式がもとになっています。
・法定雇用率=(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)÷(常用労働者+失業者数)
※短時間労働者は1人を0.5人として計算
※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人として計算(短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人して計算)
ずっと一定ではなく、社会の変化によって法定雇用率は変動することがあります。少なくとも5年に1度は見直しがされています。
障害者雇用納付金制度について
障害者雇用納付金制度は障害者雇用促進法に基づき、設けられている制度になります。障害者を雇用する場合、施設設備の改善や職場環境の調整などにおいて、費用が発生することがあります。(例:手すりの設置や車いすの方が使いやすいお手洗いの設置など)
そのため、障害者の雇用義務を果たしている事業主とそうでない事業主とでは、経済的負担に差が生まれてしまいます。
障害者雇用納金制度の目的は、上記のような経済的負担のバランスを取る事になります。
障害者雇用納付金の金額
常用労働者が100人を超えている事業主が、障害のある方の法定雇用率を未達成の場合、不足している人数×月額5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。
(常用労働者が100人以下の中小企業には納付金の支払い義務はありません)
法定雇用率未達成の事業主が納めた納付金は、法定雇用率を達成している企業へ支給する〖障害者雇用調整金〗や〖報奨金〗、その他の助成金として活用されます。
例えば、常用労働者が100人以上の事業主で、法定雇用率以上の対象障害者を雇用している場合〖障害者雇用調整金〗として1人につき月額27,000円が支給されます。
障害者雇用の助成金
障害者雇用と関係のある助成金には複数の種類があります。ここではいくつかの助成金をピックアップしてご紹介させていただきます。
各助成金には対象となる労働者や支給条件などがあります。詳しい内容は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
厚生労働省公式HP
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介で対象労働者を雇い入れ、継続的に雇用する場合に支給されます。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)は、ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介により、就職が困難な障害のある方を一定期間雇い入れた場合に支給されます。
目的は、障害のある方の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解の促進などを通し、早期就職の実現や雇用機会を作り出すことです。
支給額は1人につき、下記の通りになります。
1.対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3毛月(最大6ヶ月間)
2.1以外の場合、月額最大4万円(最長3ヶ月)
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
障害者短時間トライアルコースは、障害者トライアルコースと名前が似ていますがこちらは継続雇用することを目的としています。
障害のある方を一定期間、試行的に雇用するもので雇い入れ時の週の所定就労時間(10時間以上20時間未満)を本人の体調や職場への適応状況を見つつ、同期間中に20時間以上にすることを目指します。
支給額は1人につき月額最大4万円(最長12ヶ月)になります。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用納付金制度に基づく助成金の種類としては「障害者作業施設設置等助成金」や「障害者介助等助成金」などが挙げられます。
具体的には、障害のある方を雇い入れるために、職場の環境整備や必要な介助などの措置をとった場合、その費用の一部が助成金として支給される仕組みになります。また、障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、遠隔手話サービスや音声回線など、情報通信技術を使った事例でも支給対象となります。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は下記いずれかに該当する措置を継続的におこなった場合に支給されます。
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
障害のある方の雇用を促進し、職場に定着して働けるようにすることを目的としています。
障害者雇用を取り巻く環境は、法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化など、ここ数年で大きく変化しています。今後も変化していくことが予想されます。そのためにも常に最新の情報を把握しておくことが大切になります。
ネオワークス郡山では、利用者様の希望の職種へ就職できるよう、全力で支援しています🌟
ただいま利用者様を募集しています。
相談・見学・体験随時受付中です☺
お気軽にお問い合わせください✨

次回のブログでは、障害者雇用枠で就職を希望している方に向けてのブログを更新予定です💛